この記事では登録販売者試験で出題される、細かい部分の知識を問う問題を独自にまとめたものです。
勉強していて理解度は深まってきたものの、いまいち点数が伸びていない、なんてことはないでしょうか?
点数を伸ばすには、細かい部分の理解が必要となります。今回は眼科用薬について、細かい部分を問う問題を5つ抜粋しました。
ぜひマスターして、自信をつけてください。
動画の方が理解しやすい方は、動画をご覧ください。
①一般用医薬品の点眼薬は、その主たる配合成分から、人工涙液、一般点眼薬、アレルギー用点眼薬、コンタクトレンズ装着液に大別される。
こちらは誤です。
正しくは
一般用医薬品の点眼薬は、その主たる配合成分から、人工涙液、一般点眼薬、アレルギー用点眼薬、抗菌性点眼薬に大別される
です。
一般用医薬品の点眼薬の分類を問う問題です。
分類と併せて、目的も押さえましょう。
人工涙液:
涙液成分を補うことを目的とするもので、目の疲れや乾き、コンタクトレンズ装着時の不快感等に用いられる。
一般点眼薬:
目の疲れや痒み、結膜充血等の症状を抑える成分が配合されているものである。
アレルギー用点眼薬:
花粉、ハウスダスト等のアレルゲンによる目のアレルギー症状(流涙、目の痒み、結膜充血等)の緩和を目的とし、抗ヒスタミン成分や抗アレルギー成分が配合されているものである。
抗菌性点眼薬:
抗菌成分が配合され、結膜炎(はやり目)やものもらい(麦粒腫)、眼瞼炎(まぶたのただれ)等に用いられるものである。
一般用医薬品の点眼薬には含まれないですが、洗眼薬やコンタクトレンズ装着液というのもあります。
洗顔薬とコンタクトレンズ装着液で出題される部分は以下の通りです。
洗眼薬:
目の洗浄、眼病予防(水泳のあと、埃や汗が目に入ったとき等)に用いられるもので、主な配合成分として涙液成分のほか、抗炎症成分、抗ヒスタミン成分等が用いられる。
コンタクトレンズ装着液:
配合成分としてあらかじめ定められた範囲内の成分のみを含む等の基準に当てはまる製品については、医薬部外品として認められている。
②1回使い切りタイプとして防腐剤を含まない点眼薬では、ソフトコンタクトレンズ装着時にも使用できるものがある。
こちらは正です。
ソフトコンタクトレンズと点眼薬の関係を問う問題です。
コンタクトレンズをしたままでの点眼は、ソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズに関わらず、添付文書に使用可能と記載されてない限り行うべきでない。
通常、ソフトコンタクトレンズは水分を含みやすく、防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラオキシ安息香酸ナトリウム等)などの配合成分がレンズに吸着されて、角膜に障害を引き起こす原因となるおそれがあるため、装着したままの点眼は避けることとされている製品が多い。
ただし、1回使い切りタイプとして防腐剤を含まない製品では、ソフトコンタクトレンズ装着時にも使用できるものがある。
③イプシロン-アミノカプロン酸は、炎症の原因となる物質の生成を抑える作用を示し、目の炎症を改善する効果を期待して用いられる。
こちらは正です。
登録販売者試験で抗炎症成分は多く出題されますが、イプシロン-アミノカプロン酸が出題されるのは眼科用薬のみです。かなりマイナーな成分ですが、ここも覚えておきましょう!他の抗炎症成分もまとめましたので、効率よく覚えましょう!
抗炎症成分のまとめ(登録販売者試験範囲全体)
・ステロイド性抗炎症成分
デキサメタゾン、プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル、プレドニゾロン酢酸エステル、ヒドロコルチゾン、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ヒドロコルチゾン酢酸エステル等がある。
・その他の抗炎症成分
グリチルレチン酸等
カンゾウ
トラネキサム酸
ベルベリン硫酸塩
イプシロンアミノカプロン酸等
④パンテノールは、末梢の微小循環を促進させることにより、結膜充血、疲れ目の症状を改善する効果を期待して用いられる。
こちらは正です。
こちらは眼科用薬に配合されるビタミン成分を問う問題です。
眼科用薬に出題されるビタミン成分と滋養強壮保健薬に出題されるものは、出題のされ方が微妙に異なるので、それぞれを頭に入れる必要があります。
| ビタミンA (パルミチン酸レチノール、酢酸レチノール等) | ビタミンAは、視細胞が光を感受する反応に関与していることから、視力調整等の反応を改善する効果を期待して用いられる。 |
| ビタミンB2 (フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム等) | リボフラビンの活性体であるフラビンアデニンジヌクレオチドは、角膜の酸素消費能を増加させ組織呼吸を亢進し、ビタミンB2欠乏が関与する角膜炎に対して改善効果を期待して用いる。 |
| パンテノール、パントテン酸カルシウム等 | 自律神経系の伝達物質の産生に重要な成分。目の調節機能の回復を促す効果を期待。 |
| ビタミンB6 (ピリドキシン塩酸塩等) | アミノ酸の代謝や神経伝達物質の合成に関与している。目の疲れ等の症状を改善する効果を期待。 |
| ビタミンB12 (シアノコバラミン等) | 目の調節機能を助ける作用を期待。 |
| ビタミンE (トコフェロール酢酸エステル等) | 末梢の微小循環を促進させ、結膜充血、疲れ目等の症状を改善する効果を期待。 |
⑤スルファメトキサゾールは、ウイルスや真菌の感染による結膜炎やものもらい(麦粒腫)、眼瞼炎などの化膿性の症状の改善を目的として用いられる。
こちらは誤です。
正しくは
スルファメトキサゾールは、細菌感染(ブドウ球菌や連鎖球菌)による結膜炎やものもらい(麦粒腫)、眼瞼炎などの化膿性の症状の改善を目的として用いられる
です。
こちらはサルファ剤に関する問題です。
サルファ剤は皮膚に用いる薬でも出題されるので、マスターしましょう。サルファ剤のポイントをまとめましたので、ご確認ください。
サルファ剤のポイント:
・細菌感染(ブドウ球菌や連鎖球菌)による結膜炎やものもらい(麦粒腫)、眼瞼炎などの化膿性の症状の改善が目的
・スルファメトキサゾール、スルファメトキサゾールナトリウム等が用いられる。
・すべての細菌に対して効果があるというわけではなく、また、ウイルスや真菌の感染に対する効果はないので、3~4日使用しても症状の改善がみられない場合には、眼科専門医の診療を受ける などの対応が必要である。
・サルファ剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人では、使用を避けるべきである。
・作用のメカニズムは細菌のDNA合成を阻害することにより抗菌作用を示す。
皮膚に用いる薬に出題されるサルファ剤:
・スルファジアジン、ホモスルファミン、スルフイソキサゾール等
以上が、「細かい部分を問う問題 眼科用薬」の解説でした。細かい部分を1つずつ覚えていくことで、点数アップや自信につながります。ぜひ勉強にお役立てください。
試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)(厚生労働省)
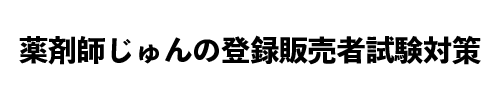
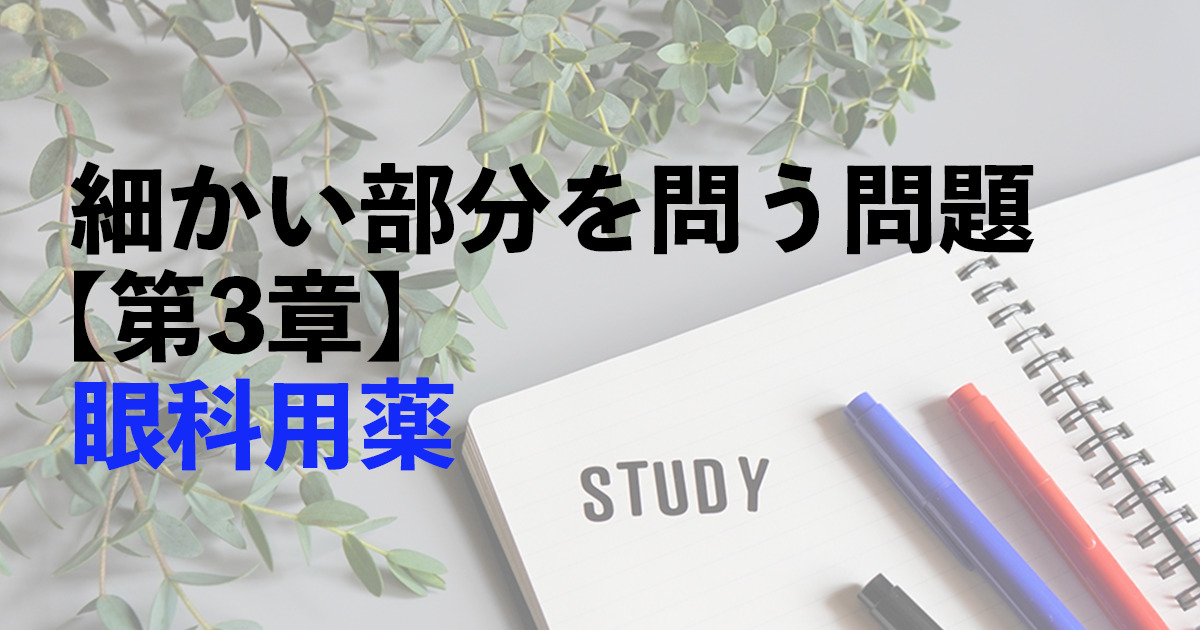

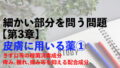
コメント